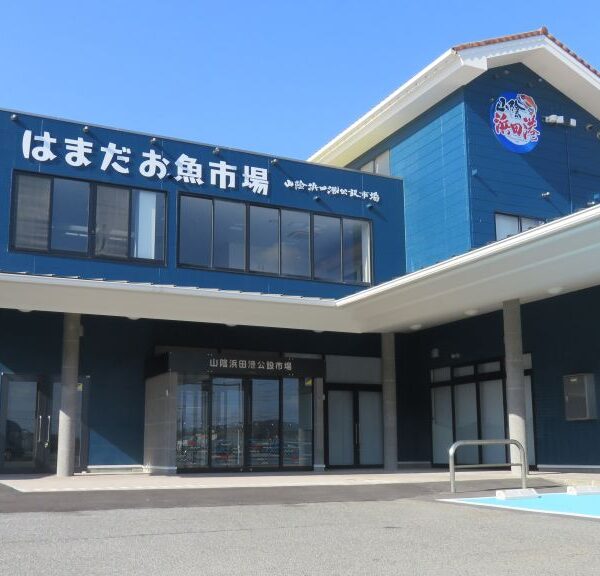ジビエの常識が変わるかも。東広島発「栄肉」の挑戦とおいしさの裏側
“ジビエ”と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?
ちょっとクセがありそう?なんとなく扱いづらそう?
そんな印象を持っている方も少なくないかもしれません。
実は私もそうでした。
けれど、東広島から生まれたジビエブランド“栄肉(さかえにく)”と出会って、
そのイメージはガラリと変わりました。
「また食べたい!」と多くの人がリピーターになるほど純粋に美味しいと感じるお肉。
そのおいしさの理由を探りに、東広島市豊栄町にある「東広島ジビエセンター」を訪ねました。
捕獲から加工まで、すべては「おいしいジビエ」のために
広島県東広島市・豊栄地区で始まった害獣駆除の取り組みから生まれたのが、
鹿や猪を扱うジビエブランド「栄肉」。
このブランドを支えるのが、東広島ジビエセンターを運営する和泉川代表と、
流通を一手に担う株式会社フレッズの曽田さんです。
和泉川代表は、もともとIT業界出身。
2016年に東広島ジビエセンターを立ち上げ、今では捕獲から加工まで一貫した体制を確立しています。

「うちは持ち込み禁止」引取り個体へのこだわり
「普通は持ち込み。でも、うちは絶対にそれをしません。」
そう語る和泉川代表。
多くの処理場では、各地の猟師さんが各々の方法で捕獲した個体が、各々のタイミングで持ち込まれています。
その方が効率よく多くの個体を処理できるからです。
そんな中で、なぜ手間をかけてでも引取にこだわるのか——
それは、捕獲の仕方・個体のしめ方・血抜きの処理、すべてが味に直結するからです。
しめ方や下処理までの時間が変わると、肉の品質にムラが出てしまうと言います。
そこで東広島ジビエセンターでは、
特定のスタッフが決まった方法で止め刺しを行った個体だけを引き取るスタイルを採用。
状態を確認し、迅速に運搬しなければならないため労力はかかりますが、
捕獲から加工まで一元管理することで、安定しておいしいジビエ肉が生まれています。
味の8割を決める!?「捕獲〜血抜き」の技術
”ジビエ“というと銃で仕留めるイメージがあるかもしれませんが、
ここではあえて罠をつかった猟を採用しています。罠にかかった個体はその都度目視でチェック。
個体の反応を確認し、外傷や極端な痩せが見られる場合は引き取りを行わないという厳格なルールを設けています。
状態を確認したあとは、“止め刺し”といわれる工程を行います。
心臓が鼓動している状態でクビの頸動脈を正確に切開し、放血するのです。
刺し傷はわずか数センチ程度。最低限の刺し傷で血抜きを行います。
わずか1分足らずでおおよその血液が抜けるので、お肉の血生臭さを抑え込むことができます。
「これで味の8割が決まるといってもいいくらい」と和泉川代表はいいますが、この工程を極めるのは並大抵ではありません。
動脈は弾力があり逃げ動くため、確実に放血するには熟練の手さばきと、なでるだけで毛が切れるほど研ぎ上げられたナイフが不可欠なのです。
徹底した準備と鍛錬が生み出すこの切れ味が、栄肉のおいしさを支えています。

徹底した衛生管理で「どこよりも安心・安全なジビエ」に
プロも驚く衛生管理
捕獲について語っていただいたところで、捕獲した個体を食肉として加工する工場の中も案内していただきました。
工場内に足を踏み入れてまず驚くのは、においがしないこと。
徹底的に清掃・衛生対策がされており、
個体をつるしている冷蔵庫ではカビ菌や浮遊菌さえほとんど検出されないというから驚きです。
これまで食肉に関わる企業がたくさん視察に来られていますが、その衛生管理に驚かれているそう。
ジビエ処理場をいくつかみている業界の方からも、
「こんなにも綺麗で管理が行き届いた工場はなかなか見られません。業界でもトップクラスだと思います。」と言われたそうです。
それもそのはず、ここでは一般的な処理場では行わないレベルの洗浄・殺菌工程が日常的に行われているのです。
●搬入前に高圧洗浄機を使用し、高温で個体の外側(毛皮部分)を洗浄。
●搬入直後の1次処理では1工程ごと(ナイフを入れるごと)に電解水で洗浄
●1次処理の仕上げとして、食品用次亜塩素酸ナトリウムを使用し徹底的に消毒
こうした徹底管理によって、日本でも稀に見る清潔環境が保たれています。
この環境に興味を持った大学などの研究者が訪れ、定期的に検査をしながら研究もされているそうです。
”もっとおいしく”を追求して
なぜこれほどまでの環境が実現できたのか、和泉川代表に聞いてみました。
「結局は“考え方”の違いです。おいしくて安全なジビエを届けたいという思いで、いろんな方法を試行錯誤したらたどり着いただけなんです。」
多くの処理場では“害獣駆除”が前提になりがちですが、栄肉は“おいしく食べる”ことが出発点。
だからこそ、“食べるため”の工程ひとつひとつにしっかりと手をかけています。
その積み重ねが、ほかではなかなか見られない衛生レベルと、
おどろくほどの品質につながっているのだと気づかされました。
家庭でも「手軽に、おいしく」ジビエを食べてもらうために
お肉は新鮮さが大事?
最後に、普段私たちが目にするスライス肉などに加工する工程を見せていただきました。
搬入して内臓を取りだす1次処理を終えたあと、すぐに加工はしないそう。
個体の大きさや状態に応じて、皮付個体の状態で3日〜1週間ほど寝かせたのちに、
皮むき・脱骨・精肉へと進んでいきます。
なぜ寝かす必要があるのか、聞いてみました。
「肉には“死後硬直”というものがあって、
死後硬直したまま骨から外してしまうと硬くなってしまうんです。
“獲れたてが一番新鮮でいい”とは限らないんですよね。
肉を落ち着かせたあとに骨から外すことで、やわらかい肉になります。
それから、寝かすときは皮付で保管することもこだわりのひとつです。
肉が乾き過ぎずしっとりするんですよ。」
”お肉は新鮮さが大事”という思い込みが、ここでひとつ崩れました。
あのしっとりとした食感の裏に、こんな丁寧な工程があったとは…目からうろこです。
お肉の美しさを引き立てる工夫
お肉を見ながら感心していると、こんな質問が投げかけられました。
「このお肉を見て、何か気づくことありませんか?」

気づくこと…なんだろう、と見つめていると、正解を教えてもらいました。
「実は、ドリップが全然出ていないんです。下に紙があるでしょう、真っ白じゃないですか?」
たしかに、スーパーのお肉では紙がひたひたになっていることが多いですが、ここでは全然見当たりません。
「余分な水分が抜けることで、旨みが凝縮されるんです。臭みやパサつきも出にくくなるし、見た目も美しく仕上がります。」
お肉をスライス加工する工程では、高性能な冷凍スライサーが使用されています。
通常よりも高速でカットでき、肉の立体感を保ったまま美しくスライスされるのが特長だそうです。


一般的なジビエは塊肉での販売が多く、初心者には調理ハードルが高いもの。
けれど、栄肉なら2mmの薄さでスライスされたしゃぶしゃぶ用や、
焼くだけで使える切身肉など、家庭でも簡単に調理できる商品が充実しています。
元料理人でもある曽田さんのおすすめは、なんと“しゃぶしゃぶ”。
「さっとお湯にくぐらせて、まずは塩だけでいただく。それだけで本当においしいんですよ」
ジビエをしゃぶしゃぶ?と驚きましたが、臭みがなく旨みがしっかり引き出されている栄肉だからこそできる食べ方なのかもしれません。
「いただく」ことが、地域の未来につながっていく
たくさんのこだわりに圧倒されながら工場を後にすると、
目の前には自然ゆたかな山々が広がっていました。

このあたりは、かつて栗畑があった場所。
現在は栽培が放棄され、自然に広がった栗の木があたりを覆っています。
イベリコ豚はどんぐりを食べて育つといいますが、
この地域の猪はなんと栗をたっぷり食べて育つそう。
まさに、自然が育てた贅沢なジビエです。
「おいしいジビエ」が育つ一方で、問題となっていることがあります。
それが、獣害による農作物被害。
獣害による農作物被害は全国でなんと年間約161億円にものぼります。
そのうちおよそ63%が鹿と猪によるものだというのです。
※農林水産省調べ いま各地でおきている鳥獣被害を考える:農林水産省
地域とともに。山の恵みを活かすサイクル
この地域も例外ではなく、獣害に悩む人が少なくありません。
それに加えて、猟師の高齢化が進み、駆除の担い手が年々減っているという現状も——。
そんな中、東広島ジビエセンターでは、なんと年間1,700頭を処理しています。
個人で害獣処理をすることが困難になった方を中心に近隣で駆除用の罠を見張ってもらい、
獲物がかかったら連絡を受けて回収する仕組みをつくっているのです。
この仕組みが良質なお肉の確保にもつながり、地域ぐるみで山の恵みを活かすサイクルが生まれています。
ただ駆除するのではなく、命をしっかり「いただく」。
そんな循環を支える企業があることで、山の未来は少しずつ守られていくのだと感じました。
そして、その循環を支えるもう一つの力が、“おいしく食べる”という選択です。
誰かの手で丁寧につながれてきたサイクルは、
食べる人がいてはじめてつながっていきます。
今日のあなたの一皿が、山の未来をちょっとだけ明るくしてくれるのかもしれません。

関連商品
YORI DORI商店街のECサイトでお求めいただけます。